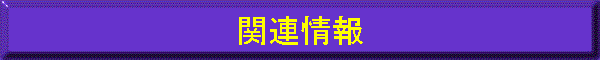
- 地元の神社の由来
- 古代史
- 蘇我氏……百済系。武内宿禰を祖とする。
- 物部氏
- 物部氏の祖神 ニギハヤヒ……扶余族の王族、(孝昭系)北夫餘(後期王朝)王 饒速日命(にぎはやひ の みこと)、神武に敗れる。別説……祖王は西蔵(チベット)ホータン月氏の王 月読命(ツキヨミノミコト)。番韓・北扶余後期王朝(濊族)のエビス系濊王(実はガド族族長)。高句麗王子 発岐(涓奴部水軍)に攻撃され、白丁軍団を率いて「天の鳥船」に乗り日本海寄りに移動南下して九州に至り、同族 陜父(義兄弟の王)の了解を得て熊本の多婆羅国に合流した。そして球磨川をさかのぼり人吉盆地の相良郡に居を構えた(のちに朝廷の傭兵となった白丁隼人の起こり)。
- 卑弥呼(-248)……ニギハヤヒの王女 ヒメタタライスズ。別説……公孫度の娘、罽須(神武)に嫁ぐ。
- 伽耶の金首露王の7王子……(別説) 3世紀はじめころ、天孫降臨の神話を持ってやってきた。九州南端から瀬戸内海を経て奈良に進出し、伽耶が滅亡した532年まで本国と密接な関係を持ち続けた。
- 神武(180頃-234)……高句麗王罽須(けいす)/貴須王/扶余王尉仇台二世/仇首(くど、くす)/若三毛野命(わかみけののみこと)/神倭イワレ彦(かむやまと……)/タケミカヅチ/ウガヤ52代
- 214 A.D.……百済王仇首(罽須・神武)在位。一族を二分して(東)扶余(帯方郡伯済国)と伊都国(唐津・博多)を支配し、自らは一大率となって九州の諸王を統括した(国史はこれを「神武大和に建国」と記す)。
- 210 A.D.……高句麗新大王の末子(女婿)罽須(けいす)(イワレヒコ)が北九州に橋頭堡を築き、公孫氏の大物主王家が投馬(とうま)国(薩摩・日向)を建てる。このとき侵入してきた扶余族イワレヒコのクメール軍団と、数年間も戦い続けたのが倭奴国のユダヤ人諸族であったが、神武と公孫氏の挟撃により頼みとするシメオンの族長大国主命(世襲名)を殺されたため、戦う気力を失い、一部は志賀島から船に乗って出雲(のちの大社)へ逃れた。また猿(作)田彦らは博多から船に乗り、東遷して秦王国の一行に参入した。その敗戦による慌ただしい移動の際の主導権争いで、「倭奴国の金印」が見失われたものと考えられる(金印は江戸時代になって、志賀島海際の田から発見された)。
- 藤原氏……伽耶系。中臣鎌足を祖とする。
- 中臣氏……ルーツはイッサカル族(南朝系)。碧眼。イスラエルのタルシシ船で、前6世紀頃、インド洋・マレー海域から北上して華北に入り、大物主命(ソロモン王)系の公孫氏(遼東の燕王)として活躍していた。二世紀以降、倭国へ渡来して安羅国(日向・西都原)建て、女王卑弥呼の邪馬台国(倭国)となっていたが、国史の中臣氏・秦氏を経て、奈良時代後期には藤原氏の系譜に参入した。三輪氏、凡河内氏も同ルーツ。
- 猿田彦……遠祖南朝ユダ系、中間に秦始皇、帝南越(旧広西省)蒼梧の秦王の子孫、 中南越の苗(ミャオ)族系弥生農民を率いた、神武の九州侵入により東遷、伊勢津彦 。秦氏(養蚕・絹織物と手工業者の集団)の王。遠祖はユダ族(南朝系)。目は茶色。奇子朝鮮にいたグループが南鮮の辰韓(秦韓)を経て対馬に渡来して居住し(北九州には上陸せず)、山口・広島・岡山・兵庫などに次々と移動して秦王国(伊勢国)を建てた。三世紀以降、倭奴国の人々とともに移動しながら、弥生農業の銅鐸文化および前方後円墳文化を遺した。のち奈良時代に、秦氏の王族らは藤原四氏(式家?)のなかに参入した。 別説……遠祖ユダヤ北朝系ガド族。猿田彦はラビの世襲名。奇氏朝鮮と同行していたが本隊と分かれて別行動をとり、銅鐸文化を持って日本海寄りに南下して対馬へ移動し、さらに北九州糸島半島に上陸して伊勢国(イスラエル人の王国)を建てた。 高句麗と連合して大国主命や東表国と戦って敗れ、出雲に亡命、銅鐸文化の旧出雲王朝を建てて栄えていた。その後出雲には神武勢力に追われた倭奴国のシメオン族らが亡命してきてガド族を駆逐して新しい出雲王朝を建て、大国主命を祀った。猿田彦の一族は山陰地方から近畿地方へと移動し、ついに伊勢国(イスラエル人の国)を今日の三重県の地に打ち立てた。
- 伊勢神宮の内宮……祭紳(アマテラス)は、天火明+ニギハヤヒ or 卑弥呼 or Urartu王国(天孫族)の祖王アラメ。
- 伊勢神宮の外宮……祭紳は豊受大神(ヤーウェ神)、元は吉野ヶ里近くの鳥栖祭殿跡の真奈井神社で祭祀されていた。この部族のルーツはシメオン族、碧眼・ワシ鼻。アレクサンダー大王東征のときバクトリア(大夏)を建国し、1世紀後、その知事ディオドトス(シメオンとチュルク族の混血将軍)が中国を統一して秦始皇帝となる。秦滅亡後、王族たちが朝鮮半島 秦韓経由で倭国(東表国・狗邪韓国)に渡来し、前1世紀、北九州の鳥栖と吉野ヶ里の地にクニを立て、猿田彦が率いる弥生農民たちも合流して倭奴国となった(前74年)。3世紀初頭、満州→朝鮮を経て侵入した北倭人の扶余族(神武)に敗れたため、急遽、博多から船に乗り東遷して秦王国(伊勢国)の一行に参入した。
- 宇佐八幡宮……南伝神道。ガド族が祭祀。ガド族の渡来経路は(インド→)中国→熊本→佐賀・長崎→福岡→奈良。 別説……東表国(ヒッタイト人、エブス人とフェニキア人の国)の「お社」。
- 邪馬台国(倭国)……ウガヤ王朝・趙国の大夫餘〜北扶余から続く百済(南扶余ありしひのふよ)と連合した公孫氏(ユダヤ人イッサカル族)の九州における植民地。
- Urartu人……フェニキア人とヒッタイト人の混血人種。Urartu王国崩壊後、シルクロードを流浪するウガヤ王朝となる。オリエントから東遷して華北に趙国(大夫餘)を建てる。その末裔は扶余人=百済人へつながる。
- 倭人……ナーガ族(シュメール人の王族)。殷人(シュメール人)は「夷」すなわちエビス/エブスと呼ばれた。
- 東表国……国東半島重藤の製鉄基地が発展して、殷人(シュメール人)が日本列島にやってきて豊前(福岡県)京都郡・宇佐八幡(バハン)を都とする東表国(豊日国)を打ち建てた(前8世紀)。神武以前の先王朝、天の王朝。豊前宇佐を中心とする南倭人のクニ。
- ヒッタイト人……国東半島重藤に製鉄基地を築いた。末裔は蘇我氏、上田氏、真田氏、青山氏?
- 弥生人……苗族
- 縄文人……港川人、オロッコ人
- 神様系図
- ミステリー
参考文献
- 日本史のタブーに挑んだ男 松重楊江 たま出版 ISBN4-8127-0167-8 C0021
その他へ戻る